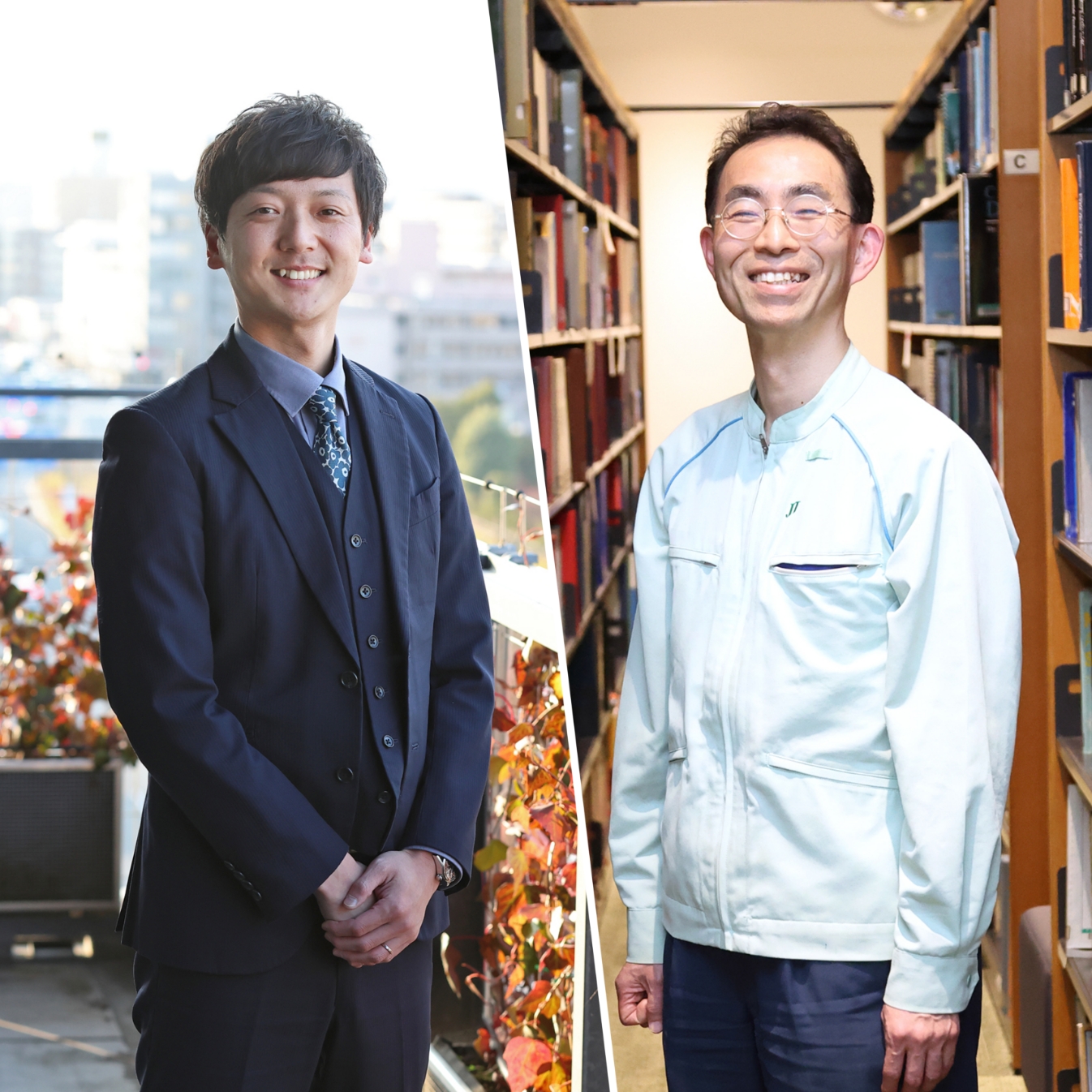01
将来への漠然とした不安……みんなの働き方って?
先日、久しぶりに同期の女性とランチに行きました。育休から復職したばかりの彼女は、パートナーと交代で育休を取り、現在は二人ともそれぞれの職場のサポートを受けながら仕事と育児を両立中。明るく話す彼女を見て、僕もいつか子育てをするのかも、と考えました。
楽しい未来を想像する一方で、子育てだけではなく、いつかは親の介護も……という心配も。そうなった時、自分の働き方ってどうなるんだろう? 制度はもちろん、当事者の声もあまり聞いたことがなくてイメージが湧かないけど、みんな仕事とライフイベントをうまく両立してるのかな?
02
「働きやすい」理由は、制度だけではないのかも
同期によると、会社には育児や介護を支援する制度が充実していて、従業員用のサイトにもガイドブックが掲載されているとのこと。これならいざという時も、自分で調べられそうで安心。
でも、制度があるだけじゃ「働きやすい」とはいえないのでは? 同期も育休に入る前は「職場のメンバーに負担をかけるかも」と、少なからず不安があったとか。確かに、僕が当事者になったとき、たとえ育休を取得する男性が増えていたとしても、同じように思うかもしれません。さらに親の介護をする年齢になれば、今より責任のある仕事をしている可能性も。その状況で、仕事と両立できるのだろうか……?
育児や介護をしながら「働きやすい」と感じるには、周囲との関係や職場の風土も大切で、「制度があること」と、「制度を利用しやすい環境」は別物なのでは? そこで、実際に仕事と育児や介護を両立している人たちと、その同僚にお話を聞いてみました!
03
周囲のサポートのおかげで、前向きな気持ちで育休取得へ
まずは、育児休職を取得したJT京都支社の中村俊祐(なかむら しゅんすけ)さんと、当時の上司の新藤和也(しんどう かずや)さんにお話を聞きしました。
 写真左は新藤和也さん、右は中村俊祐さん
写真左は新藤和也さん、右は中村俊祐さん
ゆうと:
中村さんの担当業務を教えてください。
中村さん:
営業を担当後、現在はお客様へのコミュニケーション戦略の策定担当をしています。
ゆうと:
育休はどのように取得しましたか?
中村さん:
二人目の子どもが生まれたときに、2回に分けて取得しました。一人目の育児では、私が育休を取得しなかったことで妻に大変な思いをさせてしまったと感じていたので、二人目では取得したいと前から思っていたんです。当初は子どもの出生後2カ月で育休を終了する予定でしたが、復職したタイミングで社内制度が新しくなり、育休期間の一部が有休相当扱いに。収入面での安心感が得られたため、生後半年から2回目の育休を6カ月取得しました。
上司の新藤さんに育休の制度や時期について相談したところ、「こんな制度が使えるんじゃない?」と一緒に調べてくれました。当時、京都支社では育休を取得した男性従業員がいなかったため、自分が新たなキャリアステップを提示できればいいなという想いもありました。そんな自分の気持ちも新藤さんは応援してくれて、ありがたかったです。
制度や公的支援に関する情報は従業員用のサイトに集約されていて、「妻産休暇」や「復職」といった自分のケースから簡単に調べることができたのも助かりましたね。人事部にも問い合わせたりして、情報を収集しました。
ゆうと:
長期間会社を休む不安はありませんでしたか?
中村さん:
もちろん、私の不在で業務が増えてしまうので、部署メンバーの反応は心配でした。でも、メンバーは「おめでとう! ぜひ育休を取って!」と応援してくれて、感謝の気持ちでいっぱいでしたね。皆の応援に少しでも報いたくて、引き継ぎ資料には、おすすめの巡回ルートなど、実際に業務をやってみないと分からない情報も詰め込みました。
ゆうと:
互いを思いやる、温かい職場ですね……! 育休期間中はどう過ごしましたか? また、復職後の働き方に変化はありましたか。
中村さん:
1回目の育休では、体調が完全ではない妻のサポートとして、授乳以外の家事育児を担当しました。妻には「本当か?」と言われてしまうかもしれませんが……(笑)。2回目は、妻と育児・家事を分担して家族との時間を大切に過ごしました。妻とのちょっとした会話も増え、「老後もこんな時間を過ごせるなら、あと30年仕事を頑張れるな」と感じましたね。
育休を経て、家族との時間の大切さを改めて実感し、より業務効率を意識しています。また、家庭の都合で業務に支障が出ないよう、子どものお迎えなどのスケジュールは、必ずメンバーに共有。仕事中、「そろそろお迎えの時間じゃない?」と声をかけてもらえることもあるんです。
仕事をしながら家族としっかり向き合えているのは、こうした温かい環境や、周りの支えのおかげ。メンバーが困ったときは率先して助けたいですし、私が皆さんにしてもらったように強く背中を押したいです。
ゆうと:
新藤さんには、中村さんが育休に入る際のエピソードなどをお聞きしたいです。
新藤さん:
中村さんは協調性があり、周囲と積極的にコミュニケーションをとるタイプ。また、チャレンジを楽しむ彼のポジティブな姿勢が、周囲を明るくしています。
彼の育休取得に、メンバーは皆「仕事のことは心配するなよ!」と前向きな反応でした。助け合う風土がもともと醸成されていたことに加え、チームの会議などで度々育休に関して話題にする機会があったため、どう対応するか意識できていたのだと思います。
それでも中村さんには「休むことで迷惑をかけるのでは」という想いがあったはず。それが引き継ぎ資料に表れていて、周囲からは「こんなに細かく作らなくてもいいのに(笑)」という反応がありました。そのときに引き継ぎの方法や、人に伝えるための工夫を学んだメンバーも多かったと思います。また、彼の働き方を間近で見て、育休取得に踏み出した男性従業員もいます。
ゆうと:
中村さんの姿勢や働き方が、メンバーにとって刺激になっているんですね! もっと「働きやすい」と感じる環境にするために、どうしていきたいですか?
新藤さん:
育児に限らず、誰でも長期休暇を取る可能性はあるので、業務内容を複数人で共有するなど、柔軟性を高めることが重要です。また、普段から積極的にコミュニケーションを取り、困ったことはすぐに相談し合えるようにしたいですね。中村さんの場合も、日頃のコミュニケーションが良好だったからこそスムーズに送り出せたと思います。
04
仕事のスタイルや貢献の仕方を変えて、介護との両立を
介護との両立については、JT医薬事業部 医薬総合研究所の安江克尚(やすえ かつたか)さんと、上司の小林 暁(こばやし さとる)さんにお話を聞きました。
 写真左は小林 暁さん、右は安江克尚さん
写真左は小林 暁さん、右は安江克尚さん
ゆうと:
安江さんはデータ管理の仕事をしながら、遠方のお母様の介護をされているそうですね。
安江さん:
はい。かつては研究職として働いていましたが、研究活動を支えるデータ管理業務の重要さに気付き、10年前から徐々にキャリアを変えて今はデータ管理を専任としています。
介護を始めた当初は仕事との両立が不安でしたが、社内には制度や公的支援に関する分かりやすいマニュアルや、社内SNSによる活用促進の発信もあって、安心できました。また、職場でも上司は「多様な働き方を支えるための支援制度。利用するのは当然」という姿勢を貫いていて、そういった考えが浸透してきていたタイミングだったので、ためらわずに制度利用に踏み出すことができました。

ゆうと:
介護休暇の取得について、周囲とはどのような相談をしましたか?
安江さん:
上司の小林さんには、介護をしながら仕事も滞りなく行えるよう、テレワークや介護休暇を活用したいと相談しました。快く協力していただき、さらには「会社として他にできることはないか」とまで言ってもらえて。また、担当業務を全て変えるのではなく、「どのような形でなら続けられるか」という観点で一緒に考えてくださいました。仕事での貢献の仕方を変えることで、その先のキャリアも維持することができたんです。
こういった考え方は自分の周囲だけでなく、研究所内での共通認識だと感じます。研究所内では、実験を中心とする研究職と、データ管理などのサポート業務がありますが、育児や介護などで研究を離れてサポート業務に切り替えても、いつか現場に戻った時に、経験が必ず自分の武器になると思います。
ゆうと:
周囲と相談しながら、広い視野で仕事の続け方を考えるのも、大切なことですね! テレワークや介護休暇を活用しながら仕事をするうえで、意識していることはありますか?
安江さん:
仕事を属人化せず、共有を欠かさないことです。どの仕事にも当てはまると思いますが、データ管理業務は以前から属人化しがちだったため、上司に相談して現在は複数人で分担し、いつでも情報が共有できる体制に。自身の介護とは関係なく取り組んできた課題ですが、仕事をしながら介護をする安心材料にもなっています。
今は、母親の通院に付き添う際に介護のための休暇を取得したり、月に1週間ほど実家でテレワークをしたりしています。このような働き方をしながらも仕事内容を評価していただき、昨年は社内表彰を受けました。実は、母は当初、「息子のキャリアを邪魔したくない」という想いから、なかなか介護を受けたがらなかったんです。でも、私の仕事が会社に評価されたことで安心できたようで、頼ってくれることも増えました。
ゆうと:
小林さんは、安江さんの人柄や働き方をどう感じていますか?

小林さん:
安江さんはデータ管理業務に深い知見があり、また、誰に対しても明るく、頼りにされています。安江さんが中心となって進める業務も多いですが、彼自身が日頃から周囲とコミュニケーションを密に取り、業務を属人化させないようにしています。
彼を見ていると、もしもの時に協力し合える体制はもっと整えられるはずだな、と。研究所は専門性が高い仕事が多いですが、細分化すれば他の人に任せられる業務はまだまだあります。
ゆうと:
安江さんのような柔軟な働き方は、職場にとってプラスになっていると感じますか?
小林さん:
実験が中心の研究職は、「出社しないと仕事ができない」という考え方をしていた人も多かったと思います。でも、実験をする日と自宅でデータを整理する日など、メリハリをつければ、研究職でも柔軟に働くことは可能。テレワークなどを活用して、介護をしながらでも良いアウトプットができる安江さんの働き方は、周囲にも「こういう働き方もできるんだ」と影響を与えているのではないでしょうか。
彼を含め、職場は多様な働き方を受け入れる風土が整っています。私自身も子育てでテレワークをすることがありますし、理由を問わず休みやすい環境。ただ、この風土を支えているのは、日頃のコミュニケーションによって築かれた信頼関係です。面談のような形式張った場では本音が話しづらくても、雑談なら相手の考えがよく分かることもありますよね。私は「報連相」に加えて、気軽なコミュニケーションである「雑相」も大切にし、互いに本音で話し合える環境をつくっていきたいです。
05
人事部ができる環境づくりで、心の余裕を生み出したい
制度の使いやすさや、お互いを助け合う雰囲気づくりには、制度や環境を“整える”ことも欠かせません。そこで、JT 人事部で制度設計を担当している田中佳奈子(たなか かなこ)さんと山崎志おり(やまざき しおり)さんに、取り組みについてのお話を聞きました。
 写真左は田中佳奈子さん、右は山崎志おりさん
写真左は田中佳奈子さん、右は山崎志おりさん
ゆうと:
皆さんのお話を聞いて、利用者のことを想った制度だなと感じています。そんな制度の利用促進のために、どんなことに取り組んでいるのでしょうか?
田中さん:
私たち人事部は、従業員が必要な制度を利用し、十分に能力を発揮して自己実現できる環境を目指しています。制度や「仕事と家庭の両立支援ガイドブック」の更新、社内外の制度についての問い合わせ対応はもちろん、従業員用のサイトやSNSを活用して情報を発信。最近では、従業員が不安なく育休を取得でき、また当事者以外にも育休への興味を持ってもらえるよう、ストーリー仕立てで育休取得者の心境を描くアニメーション動画も制作しました。制度の見直しについては社外にもプレスリリースを発信しており、これが従業員にとって「会社が制度を公にしているからこその安心感」につながっていればうれしいです。
制度利用者の周囲が気持ちよく応援できるようにすることも、私たちの役割です。「仕事と家庭の両立支援ガイドブック」には、上司と部下のコミュニケーションといった制度利用者との関わり方も掲載。また、「従業員の長期休職をきっかけに属人化していた仕事を分担しよう」といった、心がけてもらいたいことも紹介しています。
ゆうと:
制度を利用する人だけでなく、その周囲もサポートしているんですね。今後注力したいことはありますか?
山崎さん:
制度についてだけでなく、制度に込めた想いなども改めて周知していきたいですね。加えて、実際に制度を利用する人の声を届けたり、「この社内制度とこの公的支援を活用しては?」といったコーディネートをしたりして、より制度を身近に感じてもらえるようにしたいです。
また、JTにはオフィスワークだけでなく、工場勤務や研究職など、さまざまな働き方があります。あらゆる従業員が利用できる制度を目指していますが、全ての働き方に合わせると、制度が必要最小限になってしまう。そうならないために、法律の一歩先をゆく充実した制度を設計し、最初は限られた人しか利用できなくても、最終的には全ての人が利用できるように改善し続けています。今後も、現場の意見やキャリアに関するアンケート結果を参考に、幅広く活用できる制度や、それが使いやすい環境をつくり続けていきます。
利用しやすい制度や環境があれば、ライフイベントがあっても、心や時間に余裕をもって働くことにつながると思っています。ひいては、従業員の人生の「豊かさ」につながっていったら、制度企画担当者としてはうれしいですね。
06
安心して仕事ができる環境は、モチベーションにつながる
取材を通して、育児や介護をしながら「働きやすい」と感じるには、「安心感」が必要なのかも……と思いました。そして、「働きやすい」というポジティブな感情は、仕事のモチベーションにもつながるんだな、とも。
ライフイベントを抱えながらの仕事は不安がつきもの。充実した制度も大切ですが、それをためらわず活用できる環境こそが、当事者の安心感になると感じました。さらに、受動的にサポートしてもらうだけでなく、自分から情報を得て新たな働き方を模索したり、「お互い様」の精神を忘れずに周囲との信頼関係を築いたりする、能動的なアクションも重要なのだと思います。その積み重ねが、いっそう働きやすい職場風土を醸成していくのかも。サポートを受けられる環境が整っていて、実際にそういった環境で働く仲間たちがいることも分かり、僕の漠然とした将来への不安もだいぶ解消されたように感じます。まずは、未来を恐れず、今の仕事に全力を尽くします!